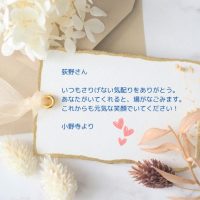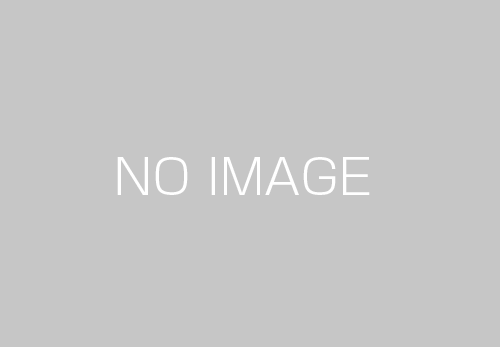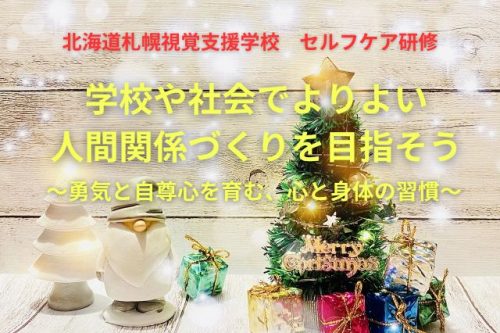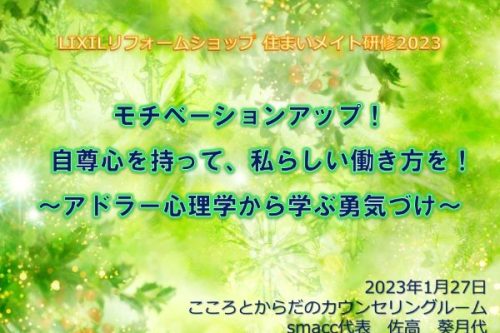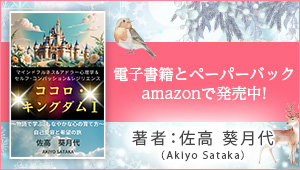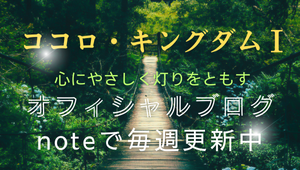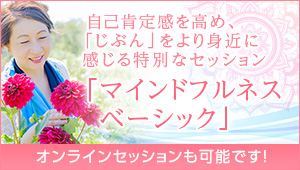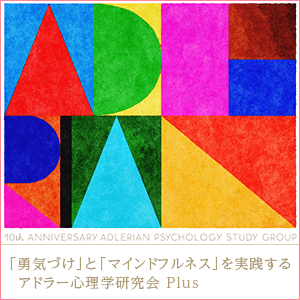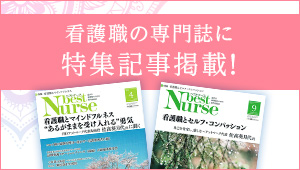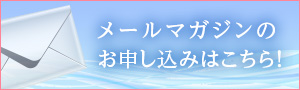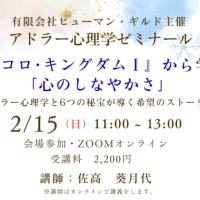こんにちは!アドラー心理学研究会Plus代表の佐高葵月代です。3月22日(土)と23日(日・オンライン)に、第143回アドラー心理学研究会Plusを開催しました。今回のテーマは、「アドラー心理学とレジリエンスで、しなやかな心作り③『繋がりが育む安定した心と共同体感覚』」です。
レジリエンスについての詳しい説明は、⇒ 1月のブログをお読みください。
繋がりとは?
レジリエンスで「繋がり(Connection)」とは、支え合える人間関係を築き、他者との関わりの中で安心感や信頼を得ることを指します。家族や友人、職場の仲間、地域社会などとの健全な繋がりが、ストレスへの対処力を高め、困難な状況でも前向きに立ち向かう力(アドラー心理学では「勇気」)を育みます。他者との関係性の中で共感や協力を実感できることが、心の回復力を強化する重要な要素となります。
共感しあうこと、笑いあうこと、会話を楽しむことは、レジリエンス(困難を乗り越える力)を高めると言われています。例えば、友人と遊びに行く、家族と定期的に出かける、誰かと一緒に食事をする。これらの何気ない日常の繋がりが、「オキシトシン」という幸せホルモンが分泌され、メンタルヘルスにとても重要な役割を果たしています。
共同体感覚とは?
アドラー心理学では、「共同体感覚」とは「他者を仲間と見なし、そこに自分の居場所があると感じること」と定義されています。身近な共同体には家族、友人、学校、職場、サークルなどがあり、さらに広い視野で見ると社会全体や人類といったレベルにまで広がります。アドラーは「自分に価値があると思えるとき、人は勇気を持てる」と述べています。
共同体感覚には、次の5つの要素があります。
•自己受容:良いところも足りないところも含めて、自分をそのまま受け入れること。
•所 属 感:「私はここにいてもいい」という安心感を持つこと。
•相互信頼:自分が周囲を信じ、また自分も信じられていると感じること。
•相互協力:責任を一人で背負うのではなく、互いに支え合うこと。
•貢 献 感:自分が役に立ち、価値のある存在だと感じること。ただし、自己犠牲ではなく健全な貢献が大切!
信頼が脳を変える
信頼できる人が側にいると、私たちは安心感を得ることができます。この安心感は、オキシトシンの分泌を促し、周囲の人の考えや感情に気づきやすくなります。オキシトシンが増えると、思いやりの心が育ち、直観力が鋭くなり、大切な人との信頼が深まるとされています。また、オキシトシンの働きによって、脳の報酬系が活性化し、相手を思いやることそのものが心の満足に繋がります。こうした仕組みが、「共同体感覚」における「貢献感」に結びついていきます。
今回のグループワークでは、共同体感覚になぜ「自己受容」が含まれ重要視されているのかについて意見を出し合いました。ご意見のひとつに「自己受容ができていないと、共同体にいても、所属感を感じられず疎外感がある」という心に響くものがありました。また、「自分をジャッジしないことで、相手を受容できるのでは」というご意見も。

自分が「不完全であるという勇気」を持つことで、相手も同じように不完全であることを認めることができ、受け入れることができるようになるのかもしれません。
そして、2つめのグループワークでは、あなたが共同体が平和で円滑に運営されるために意識するポイントは?というテーマで、日々実践している内容を話し合いました。さすがアドレリアンが多いことから、横の関係を意識したり、言葉遣い、話だけではなく感情も「聴く」という実践者の意見もありました。共同体という距離が近い関係でも、お互いの心理的、物理的距離の取り方を意識するという方もいらっしゃいました。
今月のまとめ
- 誰かと繋がっているという感覚が、心の安定とレジリエンスを育む
- 共同体感覚は、自己受容・所属感・信頼・協力・貢献感の5つの要素から成る
- 信頼感は脳に良い影響を与え、思いやりや共感を強める
- 共感的なコミュニケーションを実践することで、より深い人間関係が築ける
次回のご案内
次回、第144回アドラー心理学研究会Plusは、4月19日(土)札幌市民交流プラザ控室403、20日(日)ZOOMで開催します。
テーマは「アドラー心理学とレジリエンスで、しなやかな心作り④『思考のクセに気づく!レジリエンスを鍛える自己認識ワーク』」です。自分の行動を決める思考のクセに気づき、より自己認識を深めるテーマです。アドラー心理学の「ライフスタイル」にもぐっと迫ります。ぜひ、ご一緒しましょう!
⇒ 詳細とお申込みは、こちらから。