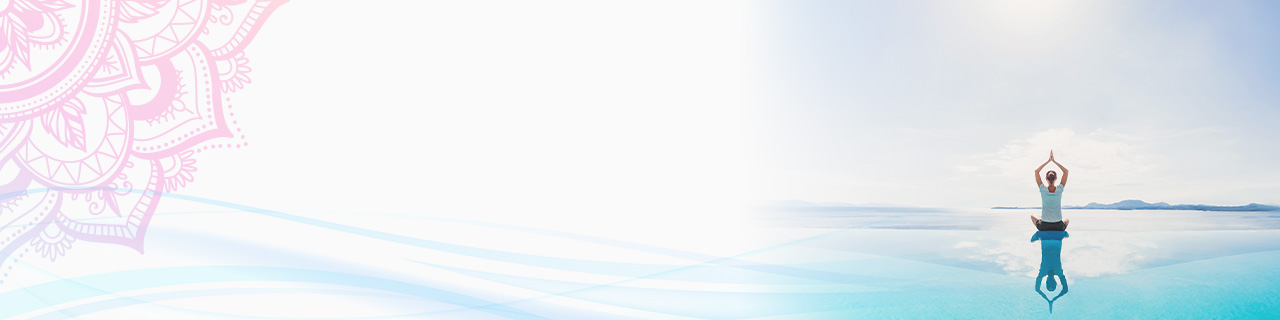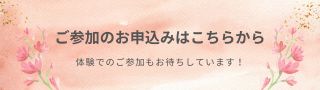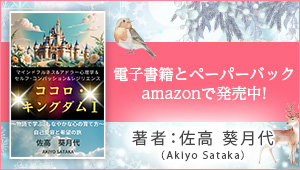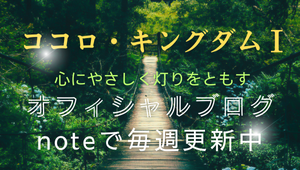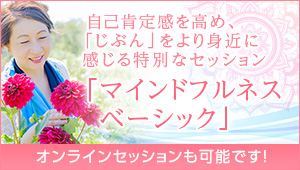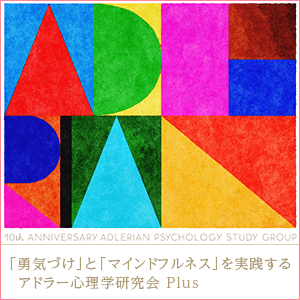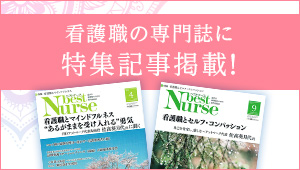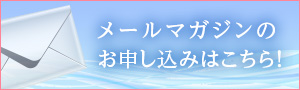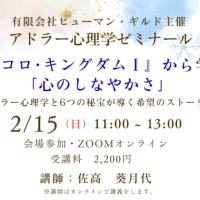smaccのヨーガについて
smaccでは、伝統的なヨーガをもとに、医療現場でも活用されている「ヨーガ・セラピー」と、心を落ち着ける「マインドフルネス・ヨーガ」を取り入れたレッスンを行っています。これらのヨーガは、ただ体を動かすだけでなく、呼吸や心の状態にも意識を向けることで、心身のバランスを整えることを目的としています。
⇒マインドフルネスについて詳しくはこちら。
ヨーガ・セラピーとは
ヨーガ・セラピーは、インドで長年研究され、医療の分野でも活用されているヨーガの一種です。1920年、インドのロナワラにあるカイヴァルヤダーマ・ヨーガ研究所で、本格的な研究が始まりました。現在では、インド政府が認定するヨーガ療法士が病院などで指導を行っており、日本でも専門的な資格を持つ指導者が増えています。
日本では、1987年から木村慧心先生がスワミ・ヴィヴェーカナンダ研究財団と提携し、ヨーガ療法士の育成に力を入れてきました。そして、2003年に日本ヨーガ療法学会が設立され、今では多くのヨーガ療法士が医療機関や福祉施設などで活躍しています。
参考リンク
日本ヨーガニケタン
一般社団法人 日本ヨーガ療法学会
ヨーガの考える健康とは?
ヨーガでは、健康を「体だけの問題」ではなく、体・心・気持ちのすべてがバランスよく整っている状態と考えます。この考え方を「人間五蔵説(にんげんごぞうせつ)」といいます。人の心と体は、5つの層(さや)でできているとされ、それぞれが影響し合っています。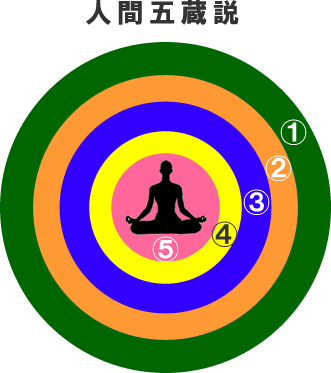
🔹 5つの層(さや)の説明
1️⃣ 食物鞘(しょくもつさや)
私たちの目に見える「体」のこと。食べたもので作られます。
2️⃣ 生気鞘(せいきさや)
「呼吸」と関係が深く、元気や活力を生み出す部分。気持ちの状態にも影響します。
3️⃣ 意思鞘(いしさや)
感情や気分をコントロールする部分。「楽しい」「悲しい」「イライラする」などの気持ちがここに関係しています。
4️⃣ 理知鞘(りちさや)
物事を判断する部分。経験や記憶をもとに「どう考えるか」を決める働きをします。
5️⃣ 歓喜鞘(かんきさや)
「本来の自分」を表す部分。ストレスや外部の影響を受けない、落ち着いた状態。
この5つの層がバランスを保つことで、心と体が健康でいられるのです。
ヨーガでバランスを整える
例えば、忙しくてコンビニ弁当ばかり食べて、睡眠も不足しているとします。
🔹 体が疲れる(食物鞘の乱れ)
🔹 やる気が出ない(生気鞘の乱れ)
🔹 イライラする(意思鞘の乱れ)
🔹 ネガティブに考える(理知鞘の乱れ)
このように、1つの層が乱れると、連鎖的に心と体の調子が崩れてしまいます。
ヨーガでは、呼吸法やポーズ(アーサナ)を通して意識を内側に向けることで、少しずつバランスを整えていきます。無理なく続けることで、心と体の調和が生まれ、ストレスに負けない健康な状態を取り戻していけるのです。