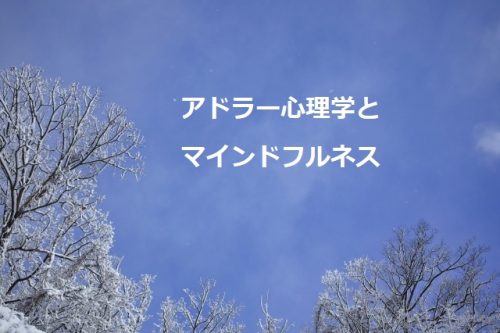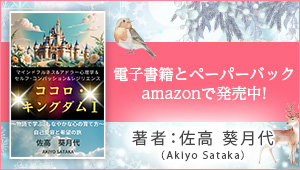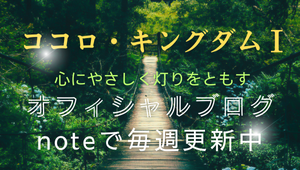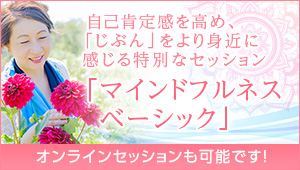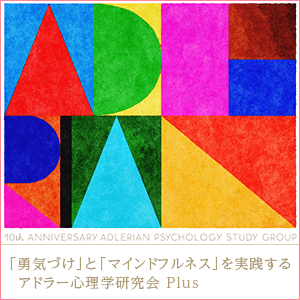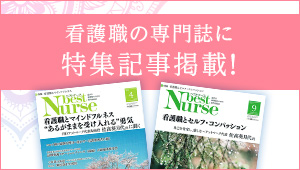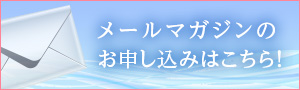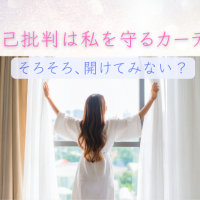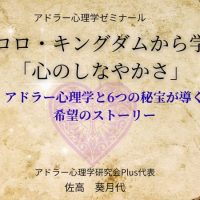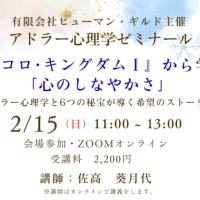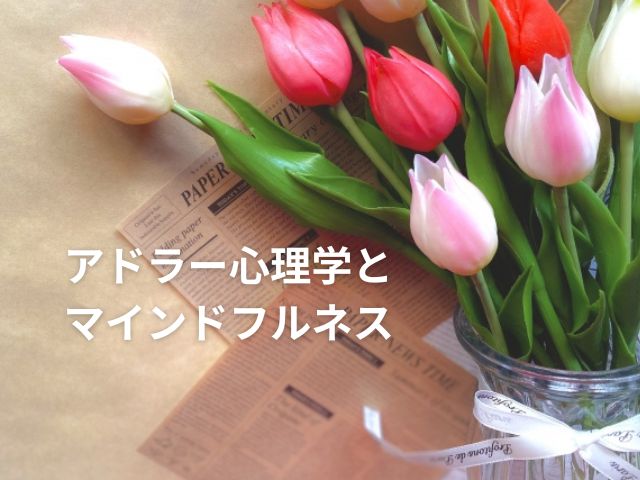
こんにちは!アドラー心理学研究会Plus代表の佐高葵月代です。5月24日(土・オンライン)と25日(日)に、第145回アドラー心理学研究会Plusを開催しました。今回のテーマは、「アドラー心理学とレジリエンスで、しなやかな心作り⑤『自制心と感情のコントロール』」です。
レジリエンスについての詳しい説明は、⇒ 1月のブログをお読みください。
1.レジリエンスの自制心とは?
自制心(self-regulation)とは、「感情や衝動に流されずに、自分の反応をコントロールする力」のこと。レジリエンスの観点では、つらい状況でも“すぐに反応せずに間を取る”ことが、落ち着きを保つカギになります。この力は、マインドフルネスやアドラー心理学の「目的論」との親和性が高く、自分の軸を保ちつつ行動できる土台になります。
2.自制心と自己認識の関係
レジリエンスにおける「自制心(self-regulation)」とは、強い感情や衝動にのみ込まれず、自分の行動や反応を落ち着いて選び直せる力のことです。この力は、生まれ持った気質だけでなく、日々の習慣や訓練によって育まれていきます。たとえば、「イラッとしたけれど言い返さなかった」、「不安に駆られたけれど、いったん深呼吸をして落ち着いた」といった行動の選択は、まさに自制心の働きによるものです。感情を感じながらも、それに巻き込まれることなく対応する柔軟さともいえます。
先月の研究会で学んだ「自己認識(self-awareness)」は、自制心を発揮するための土台です。自己認識とは、「今、自分は何を感じているのか、どんな思考や反応パターンが働いているのか」を、客観的に観察できる力のこと。自分の内面に気づけなければ、感情や思考に自動反応してしまい、その後の後悔や対人トラブルに発展しやすくなります。「今、自分は怒っているな」、「過去の失敗を思い出して怖くなっているな」と気づくことで、いったん立ち止まり、意図的に“違う対応”を選び直すことが可能になるのです。
3.アドラー心理学の感情の捉え方
アドラー心理学では、感情は「できごとによって自動的に生まれるもの」ではなく、「そのできごとをどう捉えるかによって生まれるもの」とされています。たとえば、「失敗した→恥ずかしい→もう人前に立ちたくない」という反応も、実は「失敗=価値が下がる」という思い込みが感情を生んでいます。つまり、アドラー心理学の感情の捉え方は、“感情はコントロールできる”という前提に立っています。これを「目的論」とも言い、感情にも“何らかの目的”があるという見方をします。感情は単なる反応ではなく、「何かを達成するための手段(道具)」として使われていると考えるのです。
✅ 「怒り」は相手を支配したり、自分の正当性を示すために使われることがある
✅ 「悲しみ」や「不安」も、助けを求めたり、人と繋がろうとする目的がある
✅ 自分の感情の“目的”に気づけば、感情を建設的に使い直すことができる
今月のまとめ
- 自制心は「反応の前に立ち止まる力」。感情を感じても、それに巻き込まれず選び直す力。
- 自己認識は自制心の土台。気づけなければ、制御はできない。
- アドラー心理学では「感情にも目的がある」と考え、意味の捉え直しによって感情を変える。
次回のご案内
次回、第146回アドラー心理学研究会Plusは、6月21日(土)札幌市民交流プラザ控室403、22日(日)ZOOMで開催します。
テーマは「アドラー心理学とレジリエンスで、しなやかな心作り⑥『精神的柔軟性で “見方”と“つながり”をやさしく整える』」です。レジリエンスシリーズも、いよいよ大詰めです。レジリエンスの「精神的柔軟性」は、視点の切り替えや、思考の柔軟な調整ができる力です。一方、アドラー心理学では、状況を別の視点から捉えるリフレーミングの手法を使い、意味の再解釈を行います。これらの実践的な使い方を学びます。 ぜひ、ご一緒しましょう!
⇒ 詳細とお申込みは、こちらから。